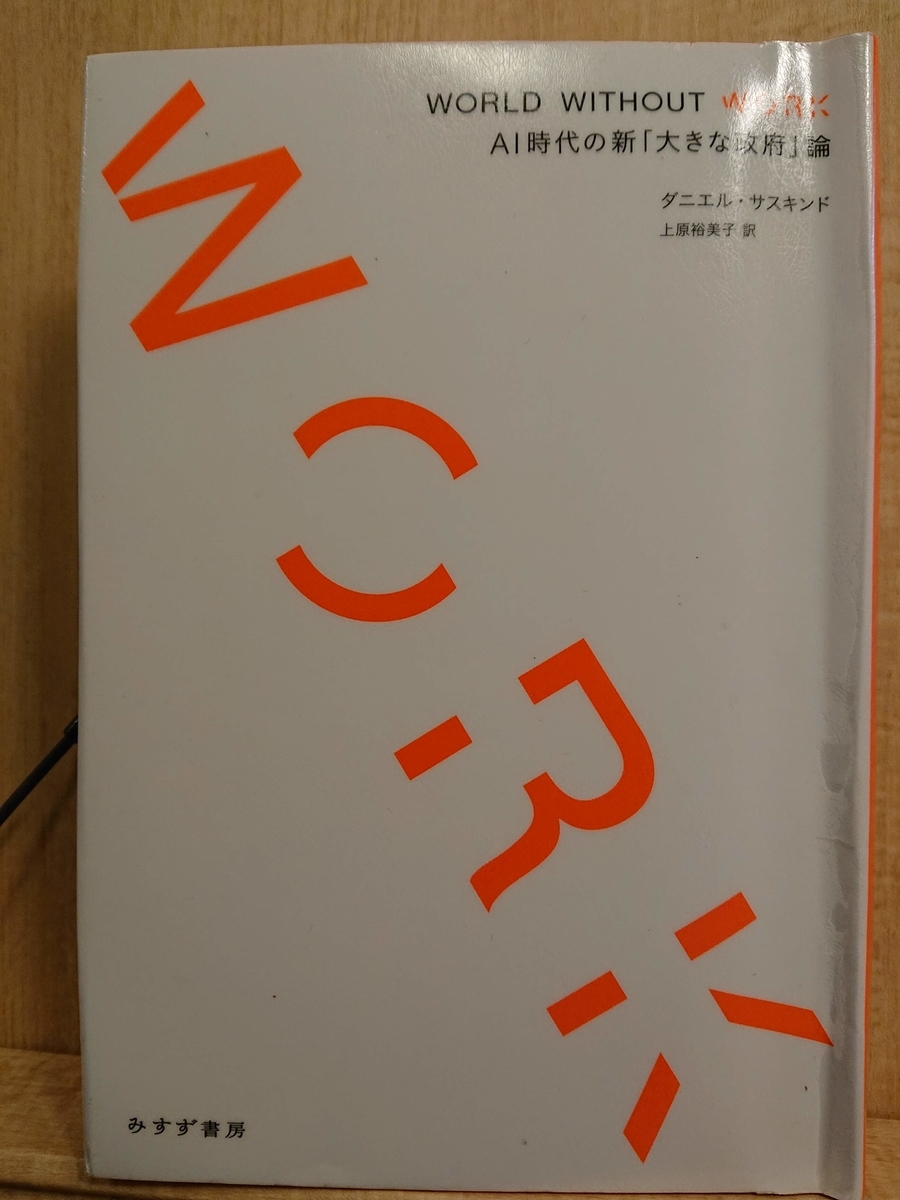WORLD WITHOUT WORK
AI時代の新「大きな政府」論
ダニエル・サスキンド
上原裕美子 訳
みすず書房
2022年3月10日 第1刷発行
原書:A WORLD WITHOUT WORK Technology, Automation, and How We Should Respond (2020)
日経新聞、2022年5月14日の書評で取り上げられていた本。記事の中では、AIで仕事がなくなったら大きな政府しか社会を維持できない、というような主張の本とかかれていて、個人的にはちょっと違うんじゃない?と興味を持った。税抜き4200円だというので、図書館でいいや、、、と思って、随分と予約者がたくさんいたけれど、予約していた。半年ばかりまって、ようやく順番が回ってきたので読んでみた。
本書の裏の説明には、
”「本書は、現代における最大の経済的試練の一つをテーマとしている。迫り来る驚くべき技術革新によって、働いて稼ぎを得るということを全員が全員行なえるわけではない世界が来たら、その先はどうするのか。…この先に待ち構える根幹的な難問、それは分配の問題だ。技術進歩は人類全体をかつてないほどにゆたかにしているかもしれないが、富を分配する従来の方法――労働に対して賃金を払う――が過去のような効果を示さなくなるのだとすれば、そのゆたかさをどうやって分かち合っていけばいいのだろう」「技術進歩は僕たちを、人間がする仕事が足りない世界へと連れていく。僕たちの祖先を悩ませていた経済問題は消滅し、かわりに3つの新たな問題と入れ替わっていく。1つめは不平等の問題。2つめは政治的支配力の問題。そして3つめは人生の意味の問題だ。…21世紀の僕たちは、新しい時代を築いていかなければならない。安定をもたらす基盤として、もはや有償の仕事には頼らない時代だ」(本書より)
イギリスの新進気鋭の経済学者が、21世紀の〈所得分配国家〉〈資本分配国家〉〈労働者支援国家〉を描き出す。”
とある。
著者のダニエル・サンキストは、オックスフォード大学経済学フェロー。同大学の AI 倫理研究所 シニア・リサーチ・アソシエイト。 キングス・カレッジ・ロンドン訪問教授。イギリス政府の首相戦略ユニット、官邸政策ユニット、内閣府などに勤めた後現職。
感想。
ふむ。なるほど。
一つの見方、一つの意見として、なるほどね、と思う。
明確に自己の主張を述べているので、ストーリとしてわかりやすい。かといって、私にとってはすごく共感する、という感じではなかった。ただ、著者と読者の間に意見の相違があったとしても、 読みやすいなと思うのは、全体の構成が素直なのだと思う。背景、脅威(どんなことが起こるのか)、対策(どうすればいいのか)が、順序だてて説明されている。他の人の論文、著書などを引用し、それについての自分の考えを明確に述べているので、世の中で言われていることと、著者がいいたいこととの違いもとらえやすい。
原注と引用文献だけで73ページ。本文298ページの大作。でも、わりと、さー--っと読める感じだった。
目次
序文
PartⅠ 背景
第1章 杞憂の歴史
第2章 労働の時代
第3章 人工知能の実用主義者革命
第4章 機械への過小評価
Part Ⅱ 脅威
第5章 タスク浸食
第6章 摩擦的テクノロジー失業
第7章 構造的テクノロジー実業
第8章 テクノロジー不平等
Part Ⅲ 対策
第9章 教育と、その限界
第10章 大きな政府
第11章 ビッグテック
第12章 生きる意味と生きる目的
序文で、著者から大きな問いが投げられる。
”生活のために働く必要がなくなったら、人間は具体的に何をするのだろう”
テクノロジーの発達によって、人々の仕事は大きく変わってきた。今は、AIによって人の労働が要らなくなる環境が広がってきている。そもそも、「働く」というのは、「生活のため」だけではないというのが私の考え方なので、この”生活のために働く必要がなくなったら、人間は具体的に何をするのだろう”という質問自体が、意味があるような、ないような。生活に困らないのに、「仕事がなくなることの恐怖」のようなものがあるとすれば、やはり、究極は「人は何のために生きるのか」という問いと同じことなのかもしれない。
PartⅠでは、技術の発達によって、人々の生活がかわってきたという背景について述べられている。産業革命によって、人による労働は大きく減った。機械によって労働を奪われる人がテクノロジー導入を反対するというラッダイト運動のような運動は、歴史的にはくり返し起きている。でも、結局、人々は機械が導入されたからといって、完全に仕事をなくしたわけではなく、他の仕事が新たに生まれてきた。あたらしい経済の「モデル」が出来てきた。
定型タスクは機械に置き換わりやすく、非定型タスクは機会に置き換えにくいと思われてきた。人間の暗黙知のようなものは、AIには無理だと思われてきた。しかし、アルゴリズム、機械学習機能の発達により、レントゲン画像の診断などもコンピューターがになえるようになってきている。
AIによって人間に代替される可能性のある仕事というのは、”職種”で語ることは難しく、”作業”単位ではどのような分野でもAIが活躍する可能性がある時代になったのだ。
古代ギリシャ、詩人アルキロコスの言葉が引用されている。
「キツネはたくさんのことを知っているが、ハリネズミは大事なことを一つ知っている」
人がキツネで、機械がハリネズミ。一つのことをできるだけでも、キツネの役に立つことがある。
どのような業種であれ、機械は、部分として人の役に立つことができるのだ。
では、AIが高度化していくことで、人間にとってどのような脅威がうまれるのか?医者よりも高精度の画像診断をコンピューターがしてくれるなら、それは患者にとっては脅威ではなくてありがたいことだろう。でも画像診断結果から機械がかってに自分の手術をするなんていわれたら脅威だ。やはり、そこには人間の医者が介在して、治療方針の対話があって、患者は安心する。ただし、医者の市場からすれば、これまで人がやってきた画像診断を機械がすれば、その診断に関わる医者の需要は落ちる。つまり、仕事が減る、ということだ。
医療に関わらず、AIの導入によって人がやる労働が減るのは、明らかだ。市場や地域によってAI導入のスピードは様々だけれど、過去の様々なイノベーションがいずれは多くの業種、多くの地域に浸透していったように、AIもいずれは多くの業種・地域に浸透するだろう。そうなれば、「人間がやる仕事の絶対量」は、間違いなく減る。AI導入をしても、絶対に人でなければならない仕事もあるのだが、人に残る「仕事の種類」が、AI導入で失業した人の仕事の需要に、スキル・アイデンティティ・地域の点でマッチするとは限らない、と言っている。
いつまでも人が重要な役割を果たすとおもわれる、保育士・看護士といった仕事は、自動車生産工場での仕事を失くした人にマッチする仕事とは考えにくい。スキルという点だけでなく、アイデンティティのミスマッチもあるという。また、転居しないとその仕事に就けないのであれば、またそれも壁になる。
仕事の足りない世界(テクノロジー失業の世界)では、数の問題ではなく、人的資本(その人の適性など)のミスマッチが問題になるのだという。
そして、著者がそれに対応するために主張するのが、「大きな政府」。大きな政府によって、所得分配・資本分配・労働者支援をするというのだ。そして、ユニバーサルベーシックインカムではなく、条件付きのベーシックインカムを導入すればいいのだ、と。
人はなぜ仕事の意味に執着するのか。
社会学者マックス・ウェーバーは、その理由は宗教にあると考えた。プロテスタント教徒にとっては、労働によって自分の魂は救済されるに値すると考えられた。労働は、信仰心を示すものだったのだ。
今の時代はどうだろうか?魂の救済のために働いていると答える人は多くはないだろう。
一方で、「お仕事は何をなさっているんですか?」パーティーなどで初対面の人と会話すれば、決まってでて来る質問だ。どんな仕事をしているか、それが当人の人となりについて重要なことを語っているという想定が少なからずあるから。
仕事は、当人にとっての意味だけでなく、意味ある生活を送っていることを他人に示し、場合によっては他界ステイタスと社会的評価を得られるという、重大な社会的側面を持っている、という。
そして、いまや宗教に代わって、「仕事」が、人々にとって社会的に重要なものになっている。いまや宗教ではなく、仕事が民衆のアヘンだと。
だというのに、「仕事の足りない世界」で、どうやって生きていくのか??
著者は、政府による「余暇政策」が必要だという。おいおい!そこまで政府が介入するんかい?!?!と思う。
「仕事が民衆のアヘン」とは、うまいこと言うな、と思うけれど、果たして本当にそうだろうか?
仕事の足りない世界では、経済と結びついたアイデンティティを持つ機会が少なくなるだろうと言っている。これは、ギグワーカーが増える社会でも同じことが言える。すると人は、別の場所で経済以外のアイデンティティを探し始め、それが、アイデンティティ・ポリティクスにつながっているのではないか、という。
著者の言うアイデンティティ・ポリティクスとは、自分の人種や宗教あるいは居住地ありきで政治に対する見解や認識が決定すること。この現象は現在経済の不安定さに対する一種の反動ではないか、と。経済における立場ではなく、より確実でより信頼できるものに自分の人生の意味を見出したくなるのではないか、と。
そして、それが、ポピュリスト政治につながっているのであれば、危険な兆候ともいえる、と。
技術革新が「仕事の足りない世界」を作り出すというのは、わかる。その先、「大きな政府」にたよるべしというのが著者の主張だけれど、私はそうは思わない。資本の分配というのが、政府の重要な仕事であることは変わらないと思うけれど、たぶん「余暇政策」なんかを政府に提供されるようになる前に、人は自分の生き方を見つけていくような気がする。
宗教でもなく、仕事でもなく、あらたな「民衆のアヘン」がうまれてくるのではないだろうか。アヘンといっても、悪いものではなく「体に良いアヘン」みたいなものが。
私は、人間というのはそれくらい創造性のある生き物だと思っている。
それが何なのかはわからないけれど、「定年後の人生」を考えるのと似たようなモノともいえる。
「お仕事はなんですか?」と聞かれて、「○○をしています」と答えられることのシンプルさ。サラリーマンをしているときは、会社の名前を言えばよかった。日本人なら誰もが知っている会社の名前なら、「へぇ、すごいですね」なんて言ってもらったり。
「お仕事はなんですか?」と聞かれて、会社名以外の答え、あるいは仕事ではないことであっても答えられるっていうのが、定年後には重要な気がする。脱サラしてフリーランスで仕事していてもそうかな。自分が社会に対して提供していることが何なのかをはっきりいえるかどうかって、アイデンティティとして結構重要かも。それが、稼ぎの柱かどうかは関係なく。
AIの時代なんかこなくたって、いつの時代も「なにのために働くのか」は永遠の課題だし、「何のために生きるのか」は、考えてはいけない課題なのかもしれない。
何のためかなんてわからないくても、それでも、今日も生きている。
いいよ、それで。
AIで世界が変わっているのは間違いないし、一つの見方としてはなかなか面白い本だった。
やっぱり、読書は楽しい。