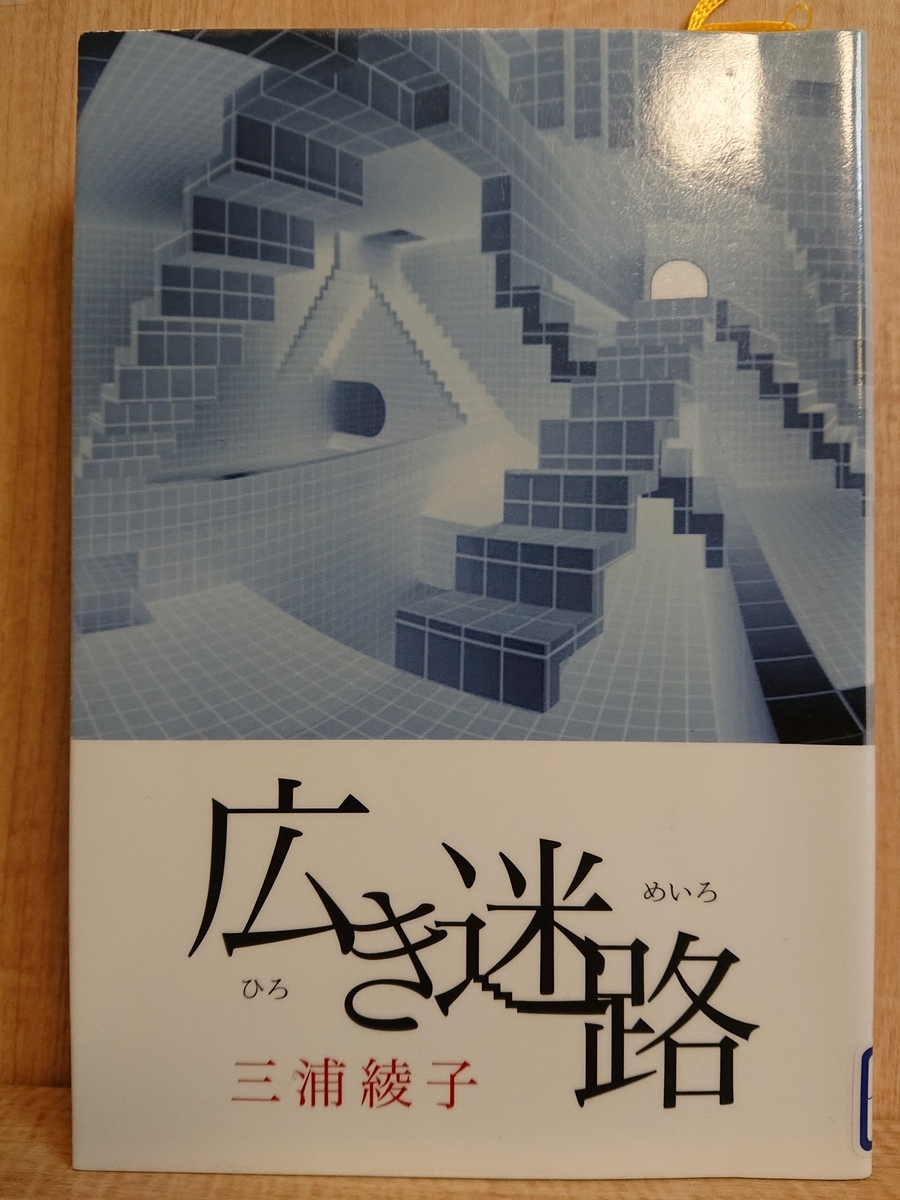言語はこうして生まれる
「即興する脳」とジェスチャーゲーム
モーテン・H・ クリスチャンセン
ニック・チェーター
塩原通緒 訳
新潮社
2022年11月25日 発行
*THE LANGUAGE GAME
How Improvision Created Language and Change the World (2022)
目次
序章 世界を変えた偶然の発明
第1章 言語はジェスチャーゲーム
第2章 言語のはかなさ
第3章 意味の耐えられない軽さ
第4章 カオスの果ての言語秩序
第5章 生物学的進化なくして言語の進化はありえるか
第6章 互いの足跡を辿る
第7章 際限なく発展するきわめて美しいもの
第8章 良循環ー 脳、文化、言語
終章 言語は人類を特異点から救う
昨日の続き。
ある言語障害が、ある遺伝子の損傷につながっていたことから、一時は、言語を遺伝的資質とみなす人もいた。でも、言語を持たないネアンデルタール人、世界各地の人間集団の何百もの下のゲノムを比較した結果、特定の遺伝子が淘汰され、言語を話せる遺伝子が残ったわけではないということが分かった。
人の言葉に関する脳の機能について。
脳の左前頭葉にあるブローカ野は発話に重要であることが分かっている。左側頭葉の上部にあるウェルニッケ野はしばしば言語の理解に関連付けられる。大人が脳卒中や頭部外傷によってこれらに損傷が起きると、発話や言語理解に問題が生じる。同じように、識字能力というのは、脳の特別な領域が関与することがわかっている。どんな文字を使っていて、どんな言葉を話している人でも、識字には、「視覚性単語形状領野」というところが関わっているそうだ。そして、それは人が読むことを学ぶにつれて徐々に出来上がる。文化的に進化した機能であるということ。 話すこと、手話をすること、を学ぶにつれて発達し徐々に言語機能に特化していく既存の神経機構に依存するそうだ。そうして子供は言葉を覚えることができる。
”言語学習は、それこそ子供の遊びのように簡単なのである。なぜなら言語は人間に学習されるよう、特に子供に学習されるように進化してきたからだ。
言語学習が人間にとってこんなにも容易なのは、人間が人間の言語を学習しているからであり、自分と同じ脳と同じ認知機能を備えた過去の何世代もの人間からそれを学習しているからである。言語学習が可能なのは、コンピューターや地球外生物命によって作られた抽象的なパターンや意味の一式を学んでいるのではなく、自分とまるで同じような過去の学習者を踏襲することによって学んでいるからなのである。”
とある。
同じような脳をもった、親をまねするから簡単。そして、その脳の構造は、何語を話している人でも同じなのだ。であれば、第二言語も母語と同じように学ぶことは可能なのだ。
それでも、人によって言語の習得、識字等はことなる。それは、あくまでもその言語にどれだけ触れているかということで、脳の機能がことなるわけではないという。
子供が家庭内で触れる言葉の量によって、子供の言葉の発育が異なる。多くの言葉に振れている子供ほど、言語は発達する。でも、結局は学校に通い始めるようになれば、振れる言葉は家庭内だけではなくなり、みんな同様に言葉を発達させていくのだという。
奇跡の人、ヘレン・ケラーは、とても有名だが、実はヘレン・ケラーより50年も前に、ローマ・ブリッジマンという人が、 目も耳も不自由な身で、英語を習得した初めての人、だそうだ。そもそも、1880年代の初めにアン・サリヴァンに指文字の技術を教えたのがローラであり、それをサリヴァンが使って、ヘレンを言語の世界にいざなったのだと。
知らなかった。
チンパンジーがコミュニケーションとして”指さし”は理解しない、という話が出てきて興味深かった。人は、言葉の奥に潜む意味を理解するように、だれかが何かを指させば、それを指して何かを伝えようとしている、と理解する。たとえば、ペンを探している風な人を見かけたときに、ペンを指させば、言葉にしなくてもペンのありかを教えていると理解する。でも、チンパンジーには、これが出来ないのだという。だれかがバナナを指さしたとしても、それをバナナがある場所を教えているとは理解せず、相手がバナナをとろうとしていると理解する。他人が親切にも有益な情報を教えようとしている、という理解はできないのだそうだ。
へぇ。。。
人は、いつから言語をつかうようになったのかは、未だにハッキリとはわかっていない。文字は化石になっても、言葉は化石にならないから。。。
言語は、ただの文化の一要素ではない。知識の蓄積と保存と伝達を可能にした。言語があったからこそ、人間の文化、社会が変化し、進化した。言語が無ければ、私たちは、目の前にいる人からのジェスチャーゲームでしか学ぶ事ができない。言語があることで、過去の発見、専門知識なども学ぶ事ができるし、ルールをつくって社会で共有することもできる。言語の出現以来、文化は変化の原動力として、遺伝をはるかに上回るものになった。
言語は、文化の変化を伝える媒体となり、更には、思考するためのツールになった。ジェスチャーから始まった言葉は、言語となり、思考のツールとなった。
とすれば、ジェスチャーゲームができないAIは、言語を使ってプレーする工夫にあふれた創造的なゲームに参加することはできない。
それこそが、「終章 言語は人類を特異点から救う」ということだ。
コンピューターには、答えられる問題と、答えられない問題がある。
コンピューターなら、
Q:1801年には誰がアメリカ合衆国の大統領でしたか?
A:1801年にはトマス・ジェファーソンがアメリカ合衆国の大統領でした。
とできる。
だけど、
Q:1600年には誰がアメリカ合衆国の大統領でしたか?
A:1600年にはエリザベス一世がアメリカ合衆国の大統領でした。
と、大間違いをすることがある。
あるいは、
Q:蜘蛛は何個の目を持っていますか?
A:蜘蛛は8個の目を持っています。
Q:私の足は何個の目を持っていますか?
A:あなたの足は二個の目を持っています。
となるとか。。。。
ちなみに、我が家のGoogle miniに
”OK google、1600年には誰かアメリカ合衆国の大統領?”
ときいたところ、
”アメリカの大統領は、ジョーバイデンです”って答えた。。。。
コンピューターは、どれだけBigdataを積み上げても、文脈を理解して答えらえるわけではないのだ・・・・。
シンギュラリティーでAIが人間を凌駕するなんて、計算の速さの世界の話だけで、宗教、哲学、芸術、、、、やはり人と人とがコミュニケーションするために生み出される文化をAIが作り出せる事はない。。。
AIが音楽や、文学を作る事例はあるけれど、それだって、所詮誰かからの借りものの組み合わせ。
言語は、文化だ。
ちなみに、著者のひとりモーテン・H・クリスチャンセンはデンマークの人だけれど、デンマーク語というのは、とても難しいらしい。母音が40個以上あるのだそうだ。日本語は、あいうえお、5個しかない。英語で13~15個(国によって違うのだろう)。それに比べて、40個って、、、。英語を学ぼうとしていることが、ラッキーなことであると思おう。。。
『言語はこうして生まれる』、つまり、コミュニケーションを取ろうというところから生まれる。子供も、自分から発信していくことで言葉を覚える。と、考えると、第二言語の学習も、相手の発信を聞いているだけではなく、自分から発信する訓練が有効なのかもしれない。でも、正しく発信(発話)するためには、正しい音がきき取れないといけない。だから、リスニングとスピーキングはセットなのだ。
なかなか、読みごたえのある、面白い本だった。
言語に限らず、研究というのは、さらなる研究で学説が覆されることがある。そうある可能性があるとわかっていても、今できる最大限で研究し、自分の仮説を証明しようとするのが、学者だ。本書は、著者らの言語研究へのそんな熱意溢れる一冊。
面白かった。
やっぱり、読書は楽しい。